自閉症スペクトラムの特性に自分と他人との境界があいまいであると言う問題があります。
うちの子供達にもその特性ははっきりとみられます。
息子の場合は会話の中で出てくるものだけですが、娘の場合、行動にも出ています。
会話の中に見られる自他境界の問題はこちらの記事に書いています。
娘は小学4年生になった現在、外では自分と他人の境界ははっきりと認識できているようですが、どうも家族の中には境界がなく、自分の境界の中に取り込んでしまっているようです。
なので娘は学校で問題のある行動はほぼなく自分からトラブルを起こすことはありません。なのに家では毎日のようにトラブルになりパニックを起こしています。
落ち着いている時はソーシャルスキルトレーニングなどで学んだように人にものを頼む言い方や家族との会話もスムーズに出来るようにはなりました。
しかし瞬間湯沸かし器でちょっとしたことでもプチパニックになります。
例えば鼻がかゆい。アレルギーがあるのでしょっちゅう鼻がかゆくなります。
そうすると「ティッシュー!ティッシュどこー!!見つからない!!」と大騒ぎをします。目の前にあっても。
学校ではそのようなことは一切せず、自分で落ち着いて対処しています。
家では騒げば人がなんとかしてくれるという意識があるのです。
そのことがわかっているので無視をすると本格的なパニックの始まりです。
自分で見つけることが出来ても人を思い通りに動かすことに必死になっているので気づかぬふりをして大騒ぎし続けます。
人の手を引っ張り力づくでも無理やり探させようとします。
自分の境界の中に取り込んでいる家族は娘にとって自分の手足のような感覚であり、思い通りに動かないことが許せないのです。
娘のパニックで私も対応に行き詰まり一旦冷静になろうと離れようとしても娘はそれを許しません。意地でもすがりつき邪魔をします。
隙をついてトイレに駆け込み鍵をかけても叫びながらトイレの戸を叩き続けるのです。お風呂の戸を蹴って壊したこともありました。
なので私も冷静な対応ができず感情に任せて怒鳴ってしまうことがしばしばです。その度に後で自己嫌悪に陥っているのですが・・・。
娘は自分自身のコアとなる境界は持っており、そこへ人に踏み込まれると猛烈に反発しパニックになります。しかし、家族の境界の中にはずかずかと入ってくるのです。
このようなパニックは朝起きた時から宿題をする寝る準備をするなど日常生活の中で毎日のように起きています。
先日も朝から大騒ぎをしていてそのことを記事に書こうと思ったら過去記事に同じものがありました。一年近く前なのにほぼ同じことを繰り返していました・・。
この時よりはパニックの時間が短くなったこと、手をつかんで離さないなどはありますが叩いたり蹴ったりするほど暴れなくはなりました。
流石にもうすぐ10歳。幼稚園の時から繰り返している朝の支度の手順が覚えられない、自分で着替えられないなどということは娘の能力的には考えられません。
寝起きで機嫌が悪いこともあるでしょうが、学校では先生の指示や視覚支援など一切なくても体育の着替えも帰りの支度もやっているわけですから。
以前は、家族への甘えなのか、親としてこれを受け止めた方がいいのか、学校で頑張ってきたストレスなのかと色々考えていましたが最近はっきりと気づいたのです。
これは娘の自他境界の問題であると。
そして娘の現在抱える困難の多くはこの自他境界のなさが引き起こしているのではないかと。
学校でのストレスはもちろん多少はあるでしょう。でも娘は学校に行き渋ったことは今まで一度もなくどちらかというと嬉々として通っています。
目立ったトラブルもなく授業も楽しいそうです。
もちろん家ではない分の緊張感はあるので家に帰るとおしゃべりが止まらなかったりしますが、ぐったりするようなこともなく体力も有り余っています。
家族への甘え、多くのお子さんでも外での顔と家での顔が違うように多少はあることでしょう。しかし娘の場合は明らかに家族を自分の意思通り動かすことに必死でそれが即パニックに繋がっていて、それは親だけでなく同じ自閉症を持つ弟にも向かいます。このままただ受け止めるというわけにはいかないのです。
娘を守りたい気持ちと同じだけ、息子も守りたいのです。
娘のこのパニックは家族をとても疲弊させます。それ以上に本人が激しい混乱と数々のトラブルの中で自分の心を削っているのです。
今まで娘に対しては家族であれ自分と他人は別の考えを持ち別の感じ方をすること、自分が思うような行動を相手がしなかったとしてもそれは相手の決めることであってあなたには関係がないしどうしようもないことなのだと繰り返し繰り返し話してきています。
コントロールが出来るとすれば自分だけであり、他人の動向は他人の自由として諦めるしかないと。
娘は頭では理解しています。しかし感覚では腑に落ちていないのでパニックになると出てきてしまうのです。そして諦めるということ自体が娘にとってとてもハードルの高いことです。
もうすぐ娘は10歳になります。一般的にはこれくらいの年齢で自分を客観視できるメタ認知や抽象的思考が育ってくると言われています。
自閉症スペクトラム児の場合このメタ認知が付きにくかったり遅れる場合もあるそうで、周りとの関係に差が出てくる原因となりやすいそうです。
これにも自他の境界の甘さが関係しているのではと私はなんとなく思うのです。
(私は専門家でもなんでもないので子供と過ごす上で感じたことです。)
自分と人との境界がはっきりしていないということは自分自身のアウトラインが見えにくいということ。
自分のアウトラインが見えなければ自分を客観視することなど難しいと思うのです。
娘が家族に対しての自他の分化が出来る時期がきているのかどうかは正直わかりませんが、少しずつ詳しく話を続けています。
外で自他区分が出来ているなら問題ないようですが、身近な人ほど他人の領域を犯してしまう、自分の意に沿うよう無理やりコントロールしようとするということは娘自身の将来に大きな困難となって立ちはだかるものだと思っています。
図を描いて自他のエリアの話や、自分がパニックになってしまう原因が人を思い通りに動かそうとしていること、それが自分を苦しめているということを丁寧に話をしました。
これからもきっと形を変えながら同じ話を繰り返して行くでしょう。
いつか娘自身の中で腑に落ちて、他人を思い通りにするためのパニックとトラブルによる辛さから娘が解放される日まで続けていくつもりです。
朝の支度について、今までは「次なにするの?!わからない!!着替え出して!」と逆切れしていたのですが、娘と話をした上で指示も一切しない、自分が何をするのか自分で考えて行動しなさい、出来なければ学校を諦めなさいと突き放してみました。
自分はそれをやる能力はもう十分にある事、自覚を持って取り組むことなど話したので、腑に落ちたのか次の日からは自分で起き、指示もないなか自分でてきぱきと支度を済ませ学校に行くようになりました。
いつもはこれがどれくらい続くかな~という感じだったのですが、今回はこうしたほうが自分が楽だと本人も言っているだけに続きそうな予感がします。今一週間ほど続いています。
これを朝の支度だけではなく広げていけたらいいなと思っています。
これは私が娘を見ている限り、娘は自分で出来ると踏んだからです。
娘と同じようなタイプのお子さんでも状態や成長によって時期があると思います。
同じく自閉症スペクトラムを持つ息子の場合、学校などの着替えは指示なくできますが、冬季鬱傾向があるので冬になると朝は極端に動けません。支度にも介助が必要です。
息子の場合は自分で出来ることは極力自分でやろうとする子で出来ないことは本当に出来ないことなんですが、娘の場合は本人が出来ないと言っていることの大半は能力的には出来ることだったりします。
その時の調子や環境によって出来る時もあれば出来ない時もある。これが発達障害児によく見られることでしょうが、娘のように自他区分の問題から人をコントロールしようとして出来なくなっていることもあるのです。
周りも苦しいけどもパニックは本人が一番つらいこと。
この苦痛から娘がいつか解放される日がやってくることを願っています。

アスペルガー・ADHD 発達障害 シーン別解決ブック―この誤解されがちな子どもたちを家族の力で育てよう (主婦の友新実用BOOKS)
- 作者:司馬理英子
- 出版社/メーカー:主婦の友社
- 発売日: 2013/12/11
- メディア:単行本(ソフトカバー)
- この商品を含むブログを見る
息子作やる気袋 pic.twitter.com/BRewBoadcP
— なないお (@Nanaio627) 2015, 6月 11やる気のある時にやる気を吹きこんでおいてやる気のなくなった時に吸い込むんだって(´・ω・`)
— なないお (@Nanaio627) 2015, 6月 11スポンサードリンク










![Temple Grandin [DVD] [Import] Temple Grandin [DVD] [Import]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51lGcNW5Z4L._SL160_.jpg)
































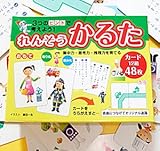








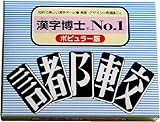



















































![実践障害児教育 2015年8月号 [雑誌] 実践障害児教育 2015年8月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51F14Eub5SL._SL160_.jpg)




![edu (エデュー) 2013年 08月号 [雑誌] edu (エデュー) 2013年 08月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51FgxOllHoL._SL160_.jpg)

















![レインマン [DVD] レインマン [DVD]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/519EtADUelL._SL160_.jpg)


































